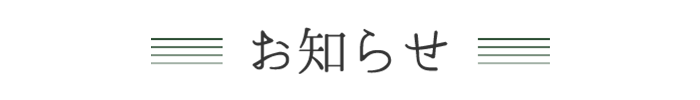
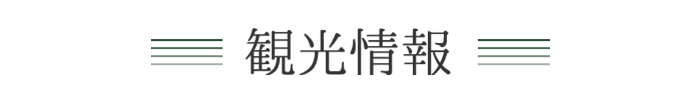
-
-

大和町観光物産協会HP
吉岡宿が舞台の史実を題材にした映画「殿、利息でござる」の元となった国恩記(こくおんき)の内容や歴史的な背景の説明、大和町の特産品・関連グッズ等の販売を行う大和町の観光案内所です。
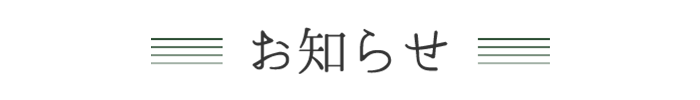
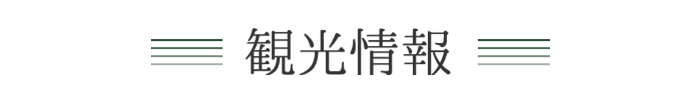

大和町観光物産協会HP
吉岡宿が舞台の史実を題材にした映画「殿、利息でござる」の元となった国恩記(こくおんき)の内容や歴史的な背景の説明、大和町の特産品・関連グッズ等の販売を行う大和町の観光案内所です。