(第5回)これからの大和町議会のあり方ゼミナール発表会を開催しました

概要
- 日時:令和4年3月26日(土曜日)午後3時00分から
- 会場:大和町役場 3階 301会議室
- 参加者:議長、あり方ゼミナール研究員17名 町議会議員18名
- 講師:東北大学大学院 情報科学研究科 准教授 河村 和徳 氏
- ファシリテーター:公立宮城大学 事業構想学群 教授 平岡善浩 氏
- 内容:発表会「私たちの議会」
これからの大和町議会のあり方ゼミナール 発表会
令和4年3月26日(土曜日)に大和町役場3階301会議室において、(第5回)これからの大和町議会のあり方ゼミナールが開催され、研究員17名と議員18名が参加しました。
第5回目となるゼミナールのテーマは「私たちの議会」として、前回までにまとめた内容の発表会を実施しました。
町議会議員になる前や、議員になった後の課題について、その原因や、解決策、そのことでもたらされる結果について、これまでのゼミナールで話し合われたことをグループごとに発表しました。


発表された課題区分ごとの内容
今までのゼミナールにおいて、議員になる前となった後の課題を5つの区分に整理し、その内の一つは、「家族、地域、会社の理解・協力」といった総合的な課題となる事柄であることから、それ以外についての課題を検討し、発表を行いました。
|
課題 |
原因 |
解決策 |
|---|---|---|
|
意欲・知識・能力 |
|
|
|
時間とお金 |
|
|
|
生活や仕事の変化 |
|
|
|
支援者や議員内での関係 |
|
|

議会や議員の制度を知らないことの解決策として、Youtubeなどでの情報発信の強化や、町民が議会と関わるイベントの開催、そして女性議会や模擬議会を開催することなどが提案されました。また、若い人や、女性が議員として活躍できるために報酬の引き上げや、育休・産休などの福利厚生の充実などの提案もありました。
併せて議会の多様性の確保ためには、町の委員会や地域の役員に女性の登用を増やすことが必要で、そのためにも女性が一歩を踏み出す後ろだてが大切になるという意見も出されました。
地域の課題を埋没させないために、議員を地区ごとの推薦制にすることにより、支援者とのコミュニケーションが図られ、区長と議員の共同連携により町の行政に反映する機会が増えるという発表もありました。
最後に東北大学大学院河村和徳準教授から講評をいただきました。
河村先生は、「皆さんの意見の中で「ちょっと違うのでは」と思う話もあったと思いますが、民主主義で難しいのは、多様な意見に寛容に耳を傾ける事であり、大事なのは、なぜ議会や少数派の方がそう言っているのか、なぜ住民の方々がこんな提案を出しているのか耳を傾ける事で、意見を受け入れる度量があることを前提とした制度です。
全国1500の自治体・議会に「この5年間でなり手不足の議論があったか」というアンケートをしました。
取り組みとして委員会や組織をつくったのは7.9%で、そうして考えると、この取り組み(これからの大和町議会のあり方プロジェクト)は、ファーストペンギン、アーリーアダプターであると言えます。
本日は、中間発表会という位置づけだと思いますので、今日新しいスタートラインについたと思って頑張っていただければと思います。
多様な意見があるから、新しいエネルギーが出てきて、新しい意見が出て、クリエイティブなイノベーティブな意見や考え方ができるという発想があります。」とお話しされました。
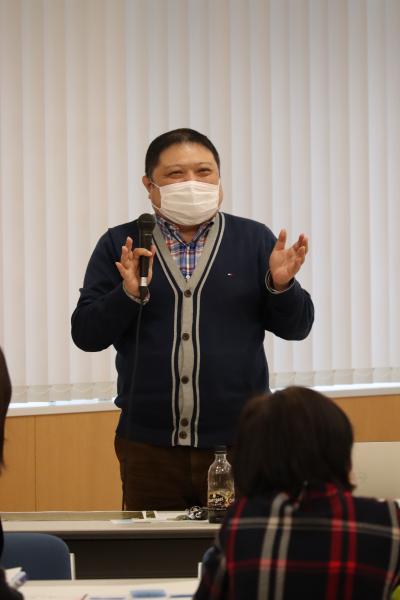
これからの大和町議会のあり方プロジェクト
令和4年度からは、発表された内容を基に、これからの大和町議会に必要な、制度や仕組みについて研究員と議員が話し合う機会が設けられます。
これからの大和町議会のあり方プロジェクトは次のステージへ続きます。
どうぞご期待ください。

参加されたゼミナールの研究員の皆さんありがとうございました。
ゼミナールで出された意見や発表の詳細は、下記資料をご覧ください。
資料
これまでのあり方ゼミナール (PDFファイル: 465.5KB)
宮城大学作成前回の振り返り資料 (PDFファイル: 619.3KB)
ワークショップの成果を展示しています
発表された内容は、開催状況の写真も交えて役場3階の議会ロビーにて、展示しております。
展示は、役場開庁日8時30分から17時30分までとなります。どうぞご覧下さい。










更新日:2024年03月24日